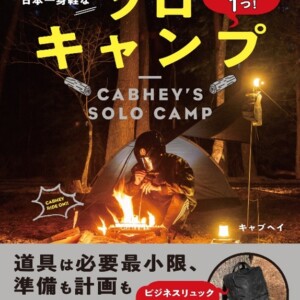わたしの初やま|#02 雨の尾瀬・父と登った里山での「街にいたら感じられなかったこと」
7年前の7月、わたしは尾瀬にいた。
「尾瀬でも行く?」
「“はるかな尾瀬”!?行く!」
群馬に引っ越した友人に会いに行くと伝えたところ、そう友人が提案してくれた。
ふたつ返事で同意したものの、尾瀬がどんなところかよくわかっていなかった。
小学校の時に歌った“あの歌”しか知識がなかったから、水芭蕉の花がゆらゆら揺れて咲き乱れる、草原やお花畑みたいなところなんだろうと想像した。今思えば、水芭蕉にゆらゆら揺れるほどの茎はないし、そもそも7月は水芭蕉には遅かったのだけど(笑)
迎えた当日はあいにくの雨模様。鳩待峠から竜宮まで行き、ヨッピ吊橋を回って鳩待峠に戻る周回ルート、約5時間の行動計画だった。5時間も歩けるかしら、と少し怯んだけど、とりあえず行ってみるか、と歩きはじめた。
真っ白な霞、濡れて色の濃くなった木道、雨に打たれて瑞々しくただそこにある草木、バラバラとレインを叩く雨の音。
自分でも不思議だったのだけれど、見るもの、聴くもの、感じるもの全ての体験にワクワクして、非日常に迷い込んだようだった。ふだん雨の日はさっさと1日引きこもりを決めこむのに、こんな雨のなか山を歩いてる!となんだかおかしかった。
楽しく会話をしていたかと思えば、急に黙って黙々と歩く。そんなことでもいちいち新鮮でわたしは興奮していたし、ただそこにある自然は美しいなと思った。
尾瀬ヶ原まで歩いてきても、相変わらず白い霧はどんよりと空に居座り細い雨は絶え間無く降りつづけ、白とグレーの世界は果てしないように感じられた。
歩くのはそんなに苦ではなかったけど、竜宮に着いた頃にはすっかり身体が冷え切っていた。竜宮小屋で食事をとったと思うけど、何を食べたのか覚えていない(笑)。ヨッピ吊橋まで行って周回する予定だったけど、やっぱり運動不足の体に雨の中の歩行は堪えたのか疲れも出てきていたので、来た道をそのまま戻ることになった。
山の鼻小屋まで戻ってきたら、ピンクやオレンジの色とりどりのレインを着た女の子がたくさんいた。なんだこの女の子たちは!と思っていたら、友人が「至仏山に登ったのかな」と教えてくれて、なんとここからまだ高い山があるのか、そしてそこへ登るのか、と思った。霧は深くて至仏山は全く見えていなかったから、高い山がそこにあることすら認識していなかった。
「山に登る人がいる」ということを、このとき初めて認識した。山の上には何があるんだろう、と想像しようとしたけれど、さっぱりだった。でも、こんなにたくさんの女の子たちが登るだけの理由が山にはあるのか、と思ったことを覚えている。
わたしの初めての山は、ピークを踏まない山だった。ただ山の中に分け入り、見たことのない自然に触れただけだった。
それでも、なんでもない樹林帯の記憶があまりに鮮明で、それから「また山に行ってみたい」と思うようになった。それでも一人で山へ行くハードルはなかなかに高く、気づいたら3年が経っていた。
————————————————————-
3年の間に、環境は変わった。
新しい街に移り住み、新しい仕事をして、新しい人と出会う。変化に慣れるにはエネルギーもそれなりに必要だし、新しい人と出会えばもちろん別れもある。まあありていに言えば転職と失恋というやつだ。
時間は無情だから、わたしの内面がどうだろうと当たり前に毎日は過ぎていくけれど、心の何処かに何かが引っかかっている。毎日を問題なく送れるだけの生きる術はもちろん身につけているのだけど、ふとした時に選択を後悔したり、日々の疲れから無性に疲れて自暴自棄な気持ちにもなったり、モヤモヤモヤモヤする日が続いて、そんな自分にまた嫌気がさしたりもしていた。
そんな中、ふと「山に行こう」と思いたった。
県内の山のガイドブックを買って、ある山に白羽の矢を立てた。標高は1000mに満たず、コースタイムは短く(往復3時間!)、実家から自宅へ帰るちょうど途中に登山口がある。これはいい。
一応家族に「山に行く」と伝えたら、なんと父が心配してついてくるという。お父さん、わたしもう30過ぎてるんだけど…と思いながらも、一人は不安だったのだと思う。ありがたく同行いただくことにした。
3月、決して有名ではない里山の登山口に車は少なかったけど、先行者が1組いて少しホッとした。自分で行く初めての山なのに、お父さんもいるんだから道迷いなんて絶対してはいけない。責任重大だ、とガイドブックのコピーとにらめっこをしながら歩きはじめた。

杉林の中をゆっくりと進んで行く。今思っても、それなりに急だったような気がする。でもとても登りやすい登山道だった。
実家の近くの山だから、こんな里山の景色は見慣れているはずなのに、父がとても楽しそうだった。「うちの前の山もこんな風だったらいいなあ」と綺麗に整備された杉並木を見ながら何度も子供のように呟いていた。
お父さんも山をいいなあと思ったんだな、となんだか嬉しかった。
杉林を登りきると、平坦な林道に出た。「なーんだ、広い道じゃん」とノルディックウォーキングが趣味の父は、ストックを使ってずんずん進む。


林道には日陰と日向が交互に現れた。暖かさを含んだ光がとても綺麗だった。
木の影や露出した木の根さえもなんだか新鮮で、わたしは自分の意思で山に来たんだな、と感慨深くなった。
そんなセンチメンタルな気分は、現れた林道の分岐に一瞬でどこかへ飛んで行った。ガイドブックを見てみるも無情な一本線が引いてあるだけで、ガイドブックの地図って、実際の道が全部書いてあるわけじゃないんだ、と困惑した(そりゃそうだ、縮尺が違いすぎる)。
「多分こっち!」と当然太い林道の方へ進みことなきを得るも、その後も地図にない(載せるほどでもない)少しの分岐や脇道が現れるたびにドキドキして、「ちょっと待って!と父の足を止めたりした。
それにしても少し下ってるしお父さん早すぎないかな、そんなに早く行ったら疲れちゃうよ…と心配していたけど、そのあと現れる登り返しに二人で「えー、また登るのー!」と弱音を吐く。
その登り返しは山頂手前の最後の登りだった。登山道には少しだけ雪が残っていて、ふたりでひいひい言いながら登る。
息切れがする、ああ辛い、しんどい、急だねえ、山頂まだかなあ。
思ってたよりしんどいなあ、でも行こうって言ったのわたしだし。
なんでわたしまた山に行こうなんて思ったんだろう。
でも、いまさら戻ってもなあ。せっかく来たのに。
そんな後ろ向きな思いが頭を何度か巡って、そしてしばらくすると頭の向こうにすうっと消えていった。
急な坂では、雪の上ではバランスが取れずに滑った。いや、実際今思えば全然たいしたことはなかったんだけど、父にストックを差し出してもらう場面まであった(笑)
そんなひいひいの最後の登りが終わると、林の中の平らな広場に出た。
「あれ?ついた?」
山頂だった。
山頂っぽいものが見えて、それに向かってずんずん歩いて、「やったー!着いたー!!」と両手をあげて達成感いっぱい、という登頂を想像していたのだけど、

初めて立った山頂は平らで山頂標識も一瞬わからないくらい地味で、思い描いていた山頂とはずいぶん違っていた。丸太のベンチがいくつもあって、ところどころに雪が残っていて、小さな小屋が建てられていた。
なんだかあっけなくて、拍子抜けして、でもなんだかおかしくて、それからやっと、山頂に着いたんだな、という達成感が湧き上がってきた。
ガイドブックには「展望はない」と書かれていたような気がしたけれど、木々の間を縫って展望が開ける場所から、すぐ近くの町並みが眼下に、遠くには恵那山や御嶽山が見えていた。北アルプスと中央アルプスのお膝元で大学生活からの長い時間を過ごした父が「こんなところから見えるんだ、すごい!」と喜んでいたのがとても嬉しくて、不思議と誇らしいような気持ちにもなった。
小屋を偵察にいった父が「昔はここにお城があったんだって」と教えてくれて、後から調べたら太平洋戦争中には敵飛行機を見張るための監視台があり、小屋はその名残だった。こんな小さい山にも歴史があることに驚いた。
山頂にいたご夫婦に記念写真を撮ってもらって、お昼ご飯を二人で食べて、周回コースで下山した。

行動時間はたった3時間だったけど、自分で行きたい山を選んで、自分で山頂に行くと決めて、刻々と変わる景色や光の具合を感じて、そして山頂にたったこの山が、もう一つのわたしの「初めての山」だった。
天気が良いと、樹林帯に差し込む光がとても綺麗なことを知った。
太陽の暖かさ、草花を揺らす風が気持ちいいことを知った。
高いところから見下ろす町の小ささや、遠くに見える真っ白な山脈の美しさを知った。
山頂に自分の足でたどり着いたことは誇らしかったし、達成感もあった。
山頂で食べたご飯は美味しくて、しんどさの先に嬉しさがあることもよく分かった。
父が一緒に登ってくれて、一緒に頑張ったこと、嬉しかったこと、楽しかったこと、怖かったこと、しんどかったことを共有できる人がいることは有り難いなと思った。
街にいたら感じられなかった色々なことを山では感じられることを知った。
そして、山に登って澄み切った気持ちは、ぼんやりして見えなくなっていた「自分を信じる気持ち」みたいなものの輪郭を取り戻してくれたような気がした。
うまく言えないけど「悲しいことがあっても、わたしはまた好きなものを見つけられた」「毎日心が疲れても、生きるためのパワーをくれるもの、自分の気持ちを向けられるものがまだあった」と思えた、そんな感じだろうか。
山に登ってよかった、また登りたい、そう思わせてくれるに十分な体験を、この小さな里山はわたしにくれた。
4年前の3月、わたしは父と夏焼城ヶ山にいた。
———————————————————————-
それから、一人でも山に登るようになった。
一人で登る山は、誰かと登る山とは違って、自分と向き合う時間をたくさんくれた。
自分で全てを決め、考えて、判断して、実行して、感じるということ。
その全ての過程に恐れも焦りも不安も恐怖も喜びも嬉しさも感動も常に隣り合わせにあるという体験そのものが、山に行き続けている理由の一つになっている。
なんていろいろ言葉を重ねても、結局のところ心に残っているのは、写真に残っていない、尾瀬のあの雨の景色だ。
あの景色は、初めてわたしが自分と向き合うことで見えた心象風景だったのかもしれない。
もう一度あの景色が見たい、でも、きっとその場所は尾瀬ではなくても良いのだ。
山にはその人だけの「何か」がある。
山に登った人の数だけ「何か」があって、その話を聞くのもとても楽しい。
山が好きな人が、もっとたくさん増えたら嬉しい。
あなたの最初の山で、「何か」が見つかりますように。


休日は山にいたい。
![.HYAKKEI[ドットヒャッケイ]](https://hyakkei.me/wp-content/themes/hyakkei2021/img/logo-bk.svg)